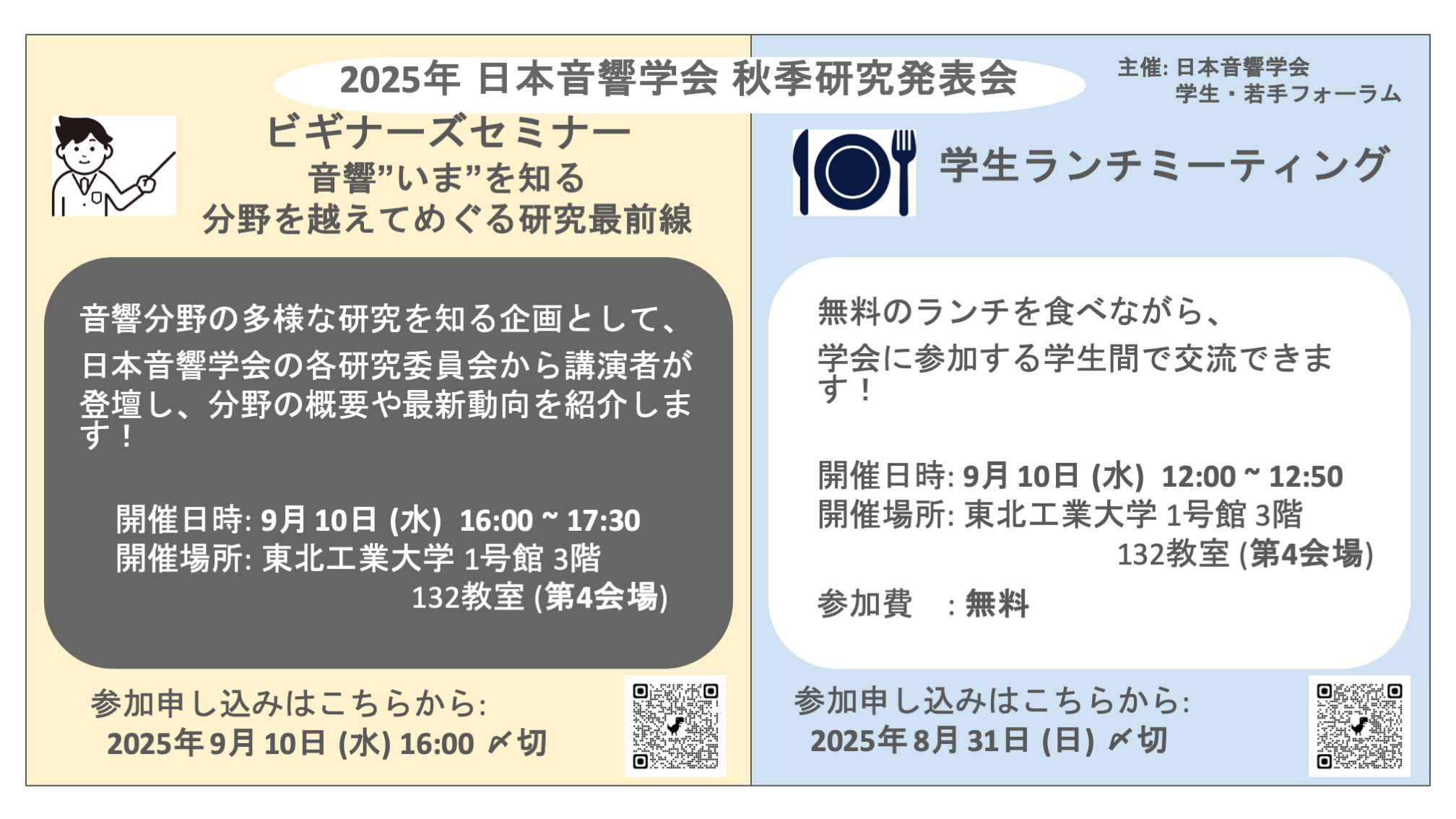◆ 音声コミュニケーション研究とは?
━♪━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本音響学会 学生・若手フォーラム
ASJ Freshニュース 第131号
2025年8月5日 発行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━♪━
はじめに
みなさんこんにちは!夏休みですね!暑さに負けないように、水分補給をたくさんしましょう!
今月号のASJ Freshニュースは、音声コミュニケーション研究および研究委員会の紹介、告知です。筆者が大学院で学んでいる音声コミュニケーション研究の面白さをご紹介したいと思います!
音声コミュニケーション研究とは
音声を用いたコミュニケーションは私たちにとってはごく普通のことですが、この一連の流れにはたくさんのプロセスが隠れています。
例えば「おはよう」と言うとき、言葉の意味だけでなく、声のトーン、スピード、抑揚などたくさんの情報が含まれています。こうした「声によるやりとり」を研究するのが、音声コミュニケーション研究です。
音声コミュニケーション研究委員会(https://asj-sccom.acoustics.jp/)では、日常の音声コミュニケーション行動を科学的に分析し、その仕組みや背景にある心理・生理的メカニズムを明らかにするとともに、発声練習支援や音響解析・合成、音声対話システムといった工学的応用も視野に入れた研究に取り組んでいます。
2021年に開設されて以降、約2ヶ月おきの頻度で研究会を開催しています。
研究例紹介
音声コミュニケーション研究会で過去に発表されていた研究を2つご紹介します。
その1「音声生成モデルの開発と音声科学・音声工学・音声言語治療・音声教育への応用」
こちら[1]は、2024年に、INTERSPEECHで有名なISCAでFellowを受賞された、上智大学の荒井隆行先生のご研究です。
みなさん、コミュニケーションをとる際、自分の「音声の生成過程」を意識されたことはありますか?この研究では、「音声の生成過程」を再現できる声道模型を作成することに取り組まれています。
模型の実際の画像がこちらです。変な形状をした筒がいっぱいある…という印象かもしれませんが、実際にこの筒に空気を通すと、日本語の「あいうえお」らしい音が聞こえます!
このような声道模型は、音声言語治療に役立てられると考えられています。実際に、言語聴覚士を志す学生に対して音声学を説明する際に、声道模型を使うことで理解促進に効果が見られたとお話しされていました。
その2「音声聴取の指標と要因」
次は、愛知淑徳大学の天野成昭先生のご研究[2]を紹介します。
居酒屋や賑やかな飲み会など、騒がしい環境で会話をするとき、「自分の声が通らなくて聞き返されることが多い」と感じた経験はありませんか?一方で、「声が通るから」と注文係を任されがちな方もいらっしゃるかもしれません。
このような「声が通る/通らない」といった現象には、単に声の大きさだけでなく、声の質や話し方など、さまざまな要因が関係していると考えられています。
近年、この“通りやすい声”に着目し、雑音の中でも聞き取りやすい声を「ポップアウトボイス」と定義した研究が進んでいます。背景にノイズを重ねた音声を被験者に聞いてもらい、音声を検出できるかどうかを評価してもらう実験を行った結果、騒音が大きくても容易に聞き取れる音声と、逆に静かな環境でも聞き取りづらい音声があることが明らかになりました。
こうしたポップアウトボイスの特性が明らかになれば、会話支援技術や公共放送、音声案内の最適化、高齢者や難聴者のQOL(生活の質)向上、さらには災害時の緊急放送など、防災・減災の観点からも大いに役立つことが期待されます。
最後に
本記事では、音声コミュニケーション研究の例を少しだけご紹介しました。
このように音声コミュニケーションに関する研究は、日常の何気ない会話から、緊急時の情報伝達、さらには最新の音声技術の進化まで、私たちの生活のあらゆる場面に関わっています。 この記事を通して、音声コミュニケーションの世界に少しでもご興味を持っていただけたら幸いです!
近日中では、2025年9月27日(土) にオンラインにて研究会が開催されます! 今回の研究会では「音声信号処理とコミュニケーション研究の融和を目指して」をテーマに、音声コミュニケーションの物理的・生理的・工学的側面と言語学的・心理学的・社会学的・教育学的側面との融合を目指した研究が発表される予定です。ぜひ気になる方はチェックしてみてください!
(大浦杏奈 学生・若手フォーラム コンテンツ班)
参考文献
[1] 荒井隆行. [特別講演] 音声生成モデルの開発と 音声科学・音声工学・音声言語治療・音声教育への応用. 音声コミュニケーション研究会資料, 2025, 5.2: SC-2025-17.
[2] 天野成昭. [招待講演] 音声聴取の指標と要因. 音声コミュニケーション研究会資料, 2025, 5.3: SC-2025-21.